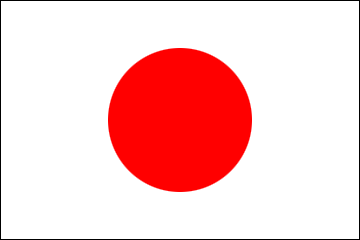2020年12月 ボリビア経済情勢
令和2年10月9日
1 マクロ経済
(1)2020年度金融計画への署名(8日付け報道)
12月7日,モンテネグロ経済・財政大臣及びロハス・ボリビア中央銀行(BCB)総裁は,経済を再構築するための合意である,2020年度金融計画(第2改訂版)に署名した。同計画では,2020年度のGDP成長率をマイナス8.4%,財政赤字を対GDP比12.3%,インフレ率(年度末時点)を1.1%上昇と試算している。今後の経済方針については,モラレス政権主導の経済モデルへ回帰し,公共投資の促進と産業化プロジェクトの再開により経済の再活性化を目指す。
(2)2021年度予算(法律第1356号)
ア 予算総額:228,357百万ボリビアーノス(主な内訳)保健省:22,830百万ボリビアーノス(約10%相当)
教育省:23,770百万ボリビアーノス(約10%相当)
国防省: 4,497百万ボリビアーノス(約2%相当)
内務省: 4,679百万ボリビアーノス(約2%相当)
経常支出:47,841百万ボリビアーノス
公共投資:40億1,100万ドル
社会的給付金:6,274百万ボリビアーノス
イ 2021年経済想定
経済成長率:4.8%,インフレ率:3.1%,財政赤字(対GDP比):9.74%,原油価格:42ドル/バーレル
(3)固定為替相場性の維持(18日付け報道)
モンテネグロ経済・財政大臣によれば,為替相場制の見直しは現時点において適切ではなく,来年度の固定為替相場制は維持される。同大臣は,いくつかの国内産業が輸入資材に依存していることを指摘し,為替相場制の見直しによるインフレーションへの懸念を示している。
(4)海外送金の減少(18日付け報道)
国際移住機関(IOM)によれば,ボリビアにおける2020年度の海外送金による歳入額は,パンデミックの影響を受け,約35%減少した。主な送金元となる国は,アルゼンチン,チリ,スペイン,イタリア,アメリカなどであったが約27,000人のボリビア人が本国へ帰国している。なお,2019年度の送金総額は13億1,800万ドル(ボリビア中央銀行発表)で,2020年11月時点では9億8,000万ドルであった。
(5)飢餓対策給付金の支給開始(2日付け報道)
12月1日,ボリビア政府は,飢餓対策給付金の支給を開始する。総額5億8,700万ドルを,約400万人に対して支給する計画。モンテネグロ経済・財政大臣は,同給付金の受給者らによって,ボリビア経済における需要が活性化すると見込んでいる。2 新たな油田の発見(19日,25日付け報道)
19日,ボリビア石油公社は,サンタクルス県のヤララX1において,1,370万バレルの原油及び768億立方フィートの天然ガスが埋蔵されている可能性のある油田を確認した旨発表した。また,25日,同社は,チュキサカ県ルイス・カルボ郡において,ガス田・ボイコボ南-X1が発見された旨発表した。当該ガス田の埋蔵量は,マルガリータ油田(国内最大級の推定埋蔵量)を上回り,ボリビアにおける埋蔵量の約11%を占める。
Repsolボリビア社が当該油田に対して,約1億ドルの投資を計画しており,2021年末までに生産が開始される見込み。
なお,ボリビアでは,2006年からの14年間に74箇所での穿孔調査が実施されたが,油田は一つも見つかっていなかった。
3 その他
(1)CADEXによるバーチャルフェア開催(1日付け報道)
サンタクルス県輸出業商工会議所(CADEX)は,第一回目の国際バーチャルフェアを開催する。経済再活性化のための投資,ロジスティック,輸出をテーマに,12月7日から12日まで開催され,JICAボリビア事務所が参加する。JICAからは,民間連携事業などの情報発信や,ボリビアにおける事業展開・社会経済開発に関心を持つ企業(19社)の情報についても掲載する。(2)付加価値税の還付(法律第1355号)
17日木曜日,付加価値税の還付に関する法律第1355号が上院で可決された。同法律は,月収9,000ボリビアーノス以下のすべての人は,領収証の提出をもって,翌月には支払い済みの付加価値税5%分の還付を受けることができる。
2021年の付加価値税還付の総額は8億700万ボリビアーノスを見込んでおり,平均して一人当たり月に450ボリビアーノスの還付がなされると計算している。
(3)高価値資産税(法律第1357号)
12月31日付けにて3,000万ボリビアーノス以上の資産を有する者は,歴年毎に,3月31日までに,資産額に応じて規定された税率に従って高価値資産税を納めなければならない。なお,現時点で同税が適用される者は全国で152人のみである。